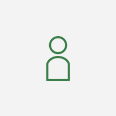大阪成蹊短期大学の教育プログラム
- 教育・研究
- 大阪成蹊短期大学の教育プログラム
在学中の学びを支え、卒業後もさらに学び続け、自らの確かなキャリアを形成するために必要な基盤的能力を育む「大阪成蹊学園 LCD教育プログラム」を全学で展開。
社会に通用する高い専門性に加え、全ての学修において「リテラシー」「コンピテンシー」「ディグニティ」を養うための「人間力教育」を実践します。

LCD教育プログラムで養う3つの力
1
リテラシー
(知識を活用して課題を解決する力)を構成する要素
能力
言語処理能力
非言語処理能力
要素
「読み」「書き」「話す」ための語彙力
文章を読み取る力
思考する力
計数を把握する力
数的処理する力
推論する力
問題解決力
情報収集力
情報分析力
課題発見力
構想力
2
コンピテンシー
(自分を取り巻く環境に実践的に対処する力)を構成する要素
| 3つの力 | 人間関係構築力 | 自己管理力 | 課題解決力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9つの要素 | 親和力 | 協働力 | 統率力 | 感情制御力 | 自信創出力 | 行動持続力 | 課題発見力 | 計画立案力 | 実践力 |
| 34の詳細要素 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
ディグニティ
(徳、品格、品性)を構成する要素
11の要素
- 1誠実性
- 2謙虚さ
- 3節度
- 4共感
- 5敬意
- 6関心
- 7責任感
- 8マナー
- 9倫理観
- 10道徳性
- 11コンプライアンス
大阪成蹊学園 教育の
質保証に係わる教学体制
理事会
常任理事会
教学改革会議
[内部質保証推進組織]
運営諮問会議
短期大学における取り組みの適切性について、企業や自治体等に所属する学外有識者からの審議、意見聴取を実施
高等教育研究所
教育政策、社会動向等に基づく教学改革プランの立案・推進
自己点検評価
委員会 教学改革の遂行や教育・研究活動の状況等について自主的な点検・評価を毎年実施
委員会 教学改革の遂行や教育・研究活動の状況等について自主的な点検・評価を毎年実施
教学改革
プロジェクト 重点テーマごとにプロジェクト管理し、PDCA体制を確立
プロジェクト 重点テーマごとにプロジェクト管理し、PDCA体制を確立
教務委員会
教育課程の編成やシラバス、成績評価等の教育実施に関する検討
各学部
教授会 教育・研究活動等に関する方針や重要事項について教員への浸透を図り、教学に係わる改革を遂行
教授会 教育・研究活動等に関する方針や重要事項について教員への浸透を図り、教学に係わる改革を遂行
FD(FD委員会)
FD委員会において基本方針、企画立案、実施等について検討。全教員がFDに参加し、教育・研究等に係わる能力と質を向上
SD(人事本部・企画統括本部)
教育・研究活動等を最適化し、より効果的な運営を図るために、全職員が必要な知識・技能を習得し、能力と質を向上
教育改革プロジェクト
240人超の教職員が参加する
21のプロジェクトチームを中心に、
全学で『教学改革』を推進。
創設以来10年間で128回の会議を開催。
平成27年度より全学的な教学改革を推進する組織体制を構築するため、教学改革会議及び高等教育研究所を設置するとともに、
才気溢れる若手教員と豊富な教育研究実績を持つ中堅・ベテラン教員による教学改革プロジェクトチームを編成しています。
教育改革プロジェクト一覧
- 英語・グローバル教育の充実
- 初年次教育・キャリア教育を核とする全学教育の実現
- 全学的なAI・数理・データサイエンス教育の構築と学内DXの推進
- 学修成果の可視化
- 産・学・地の連携による教育研究の充実
- 全学的なアクティブラーニングの推進
- インターンシップ制度の充実
- 専門演習(ゼミ)、卒業研究・卒業制作の充実
- 高大接続改革の実現
- シラバスの一層の充実
- 適切な成績評価の実施
- 授業評価アンケートの活用
- ラーニングコモンズの活性化
- 教員表彰制度の充実
- パーソナル・ブランド・マネジメントプロジェクトの推進
- 教学IRの充実
- 体系的なFDプログラムの展開
- 学修成果を発揮する各種大会・コンペティションの充実
- 教育総合改革プロジェクトの設置と改革推進強化
- 学生の成長実感の向上を図る課外活動・イベント等の充実
- 教学改革成果等の学外発信強化
本学では、全ての授業でアクティブラーニング型の授業を展開。
学生自身が調べ、考え、発表し、教員と双方向の「参加型」授業を全学で実践しています。
大阪成蹊短期大学 アクティブラーニングの『10の要件』
思考し、文章にまとめ、発表する
1
学びたくなる環境を作る
板書やスライドの工夫、履修の工夫などによって、快適な学習環境を整える
6
成果物を生み出す
学びのプロセスや成果を可視化するものとして、様々な成果物を作る
2
学び合う仲間を作る
アイスブレイクで緊張をほぐし、グループ構成の工夫などによって学び合う仲間・関係性を作る
7
振り返りを行い、更に学びたくなる意欲を生み出す
自らの成長や変化、今後の学修における課題などに気づくことができるよう、振り返りの機会を設定する
3
学びを深める活動を作る
個人ワーク、グループでのワークなど、様々な活動を並列しながら、自ら学びを深めていく活動を作る
8
適切なコミュニケーション、フィードバックを行う
1人ひとりに対する丁寧な学生理解のもと、名前を呼び、視線を向けてコミュニケーションを行うとともに、学びを広げる発言、活動への丁寧なフィードバックを心掛ける
4
適切な課題を与える
思考を刺激し、学修意欲を生み出すよう課題を工夫するとともに、回の授業に必要となる後学習・復習の課題を提示する
9
適切に評価する
多様な評価方法と観点を組み合わせ、ルーブリックを共有して、適切に評価する
5
思考をアウトプットする
書く、話す、聴く、発表するなどの活動を通じて、深めた思考をアウトプットする

10
認めて、尊重する
学修面における学生の努力を必ず認めて、大きく支援する

さまざまな学修成果を発揮する機会
- 大阪成蹊カップ プレゼンテーション大会
- English Presentation & Recitation Contest
- めざせMaestro! 大阪成蹊学園ピアノコンペティション
- 人間力を育む読書コンクール
- ビブリオバトル
- 卒業論文発表会
- 卒業制作展

企業や自治体などが実際に抱えている課題に対して、チームで協働しながら検証・調査し、
解決のための企画の提案を行うPBL(課題解決型)授業を積極的に展開しています。
企業
栄養学科 × 日清医療食品(株)
病院食献立と治療食への
展開と実践
展開と実践
日清医療食品(株)との連携のもと、「食事療法」に重点を置いて、常食からエネルギーコントロール食への展開を調理し、治療食について授業を展開。実際に作成した治療食を評価いただき、調理を通じて理解を深めました。

企業
調理・製菓学科 製菓コース × ビタミン乳業(株)
SR-1 成蹊ロールケーキコンテスト
ビタミン乳業(株)と連携し、オリジナルのロールケーキを制作。デザイン、材料発注、原価計算、レシピの作成、仕込みから仕上げまでの工程を、計画的で正確な作業を行い、コンテストを実施。学内外の審査員からフィードバックをいただき、優勝作品は吹田市旭通商店街で販売いただきました。

人文科学、社会科学、自然科学に関する教養から、人や社会を見つめ、
感性と知的好奇心を育む科目を開講
大阪成蹊短期大学
| 語学 | コミュニケーションツールとしての語学力を修得 | Active English 韓国語 中国語 海外語学演習 など |
| 情報・キャリア | 建学の精神を理解して、生涯学び続けるための基礎力を修得 | キャリアベーシック キャリアデザイン コンピュータリテラシー など |
| 国際社会と日本 | 日々の暮らしと社会との関わりを学ぶ | 暮らしと金融 ホスピタリティー論 手話コミュニケーション論 など |
| 科学と環境 | 人が健康に生きるために生命科学や自然環境について学ぶ | 日常の科学 日本の食文化 暮らしと環境 など |
| 健康とスポーツ | 健康に生涯を送るための知識と手法を学ぶ | スポーツ健康科学 スポーツ健康実技 など |
| 人間と智 | 日本の歴史の中で作り上げられた思想、文化、芸術について学ぶ | 文学と歴史 人間と宗教 心理学概論 など |
データでみる大阪成蹊短期大学の教育成果
卒業生の本学の学びに対する評価
卒業時に実施する「卒業生アンケート」では短期大学生の教育に対する高い満足度が確認され、多くの学生が成長を実感!
教育満足度
教職員のサポート満足度
成長実感度
入学満足度

授業評価アンケートによる学生の授業満足度
前期・後期授業の終了時、学生が各授業を評価する「授業評価アンケート」では、
短期大学生の授業や教員への高い満足度が明らかに!
総合評価
全体として、この授業を受けて満足した
大阪成蹊短期大学
4.38点
(+0.42)
/5.00点中(2016年比)
| 教員の授業に対する熱意を感じた | 4.41点(+0.38) |
|---|---|
| 教員は各回の授業テーマや目標、科目全体の中での位置づけを明確に説明し、計画的に授業を進めていた | 4.36点(+0.40) |
| 教員は授業の準備を十分に行っていた | 4.45点(+0.38) |
| (授業を受け)この分野の専門的知識や技術が身についた | 4.38点(+0.43) |
| (授業内容が)これから生きていくうえで役立つと思う | 4.41点(+0.44) |
| 遠隔授業では教員は授業ツールを適切に活用していた | 4.30点 ( - ) |
※2024年度前期授業評価アンケート(短大:全517科目)を対象に実施・回収。
※各問を各5点満点で採点し、設問ごとに全回答者の平均点より、特に評価の高かった項目を表示(抜粋)。アンケートの設計変更に伴い、一部の項目は2016年前期比を( )内に表記。

LCD教育プログラムで養う3つの力
1
リテラシー
(知識を活用して課題を解決する力)を構成する要素
能力
言語処理能力
非言語処理能力
要素
「読み」「書き」「話す」ための語彙力
文章を読み取る力
思考する力
計数を把握する力
数的処理する力
推論する力
問題解決力
情報収集力
情報分析力
課題発見力
構想力
2
コンピテンシー
(自分を取り巻く環境に実践的に対処する力)を構成する要素
| 3つの力 | 人間関係構築力 | 自己管理力 | 課題解決力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9つの要素 |
親和力
|
感情制御力
|
課題発見力
|
協働力
|
自信創出力
|
計画立案力
|
統率力
|
行動持続力
|
実践力
|
| 34の詳細要素 | |||||||||
3
ディグニティ
(徳、品格、品性)を構成する要素
11の要素
- 1誠実性
- 2謙虚さ
- 3節度
- 4共感
- 5敬意
- 6関心
- 7責任感
- 8マナー
- 9倫理観
- 10道徳性
- 11コンプライアンス
大阪成蹊学園 教育の質保証に係わる教学体制
理事会
常任理事会
教学改革会議
[内部質保証推進組織]
運営諮問会議
短期大学における取り組みの適切性について、企業や自治体等に所属する学外有識者からの審議、意見聴取を実施
高等教育研究所
教育政策、社会動向等に基づく教学改革プランの立案・推進
自己点検評価委員会
教学改革の遂行や教育・研究活動の状況等について
自主的な点検・評価を毎年実施
自主的な点検・評価を毎年実施
教学改革プロジェクト
重点テーマごとにプロジェクト管理し
PDCA体制を確立
PDCA体制を確立
教務委員会
教育課程の編成やシラバス、成績評価等の
教育実施に関する検討
教育実施に関する検討
各学部教授会
教育・研究活動等に関する方針や
重要事項について教員への浸透を図り、
教学に係わる改革を遂行
重要事項について教員への浸透を図り、
教学に係わる改革を遂行
FD(FD委員会)
FD委員会において基本方針、
企画立案、実施等について検討。全教員がFDに参加し、
教育・研究等に係わる能力と質を向上
企画立案、実施等について検討。全教員がFDに参加し、
教育・研究等に係わる能力と質を向上
SD(人事本部・企画統括本部)
教育・研究活動等を最適化し、
より効果的な運営を図るために、
全職員が必要な知識・技能を習得し、能力と質を向上
より効果的な運営を図るために、
全職員が必要な知識・技能を習得し、能力と質を向上
教育改革プロジェクト
240人超の教職員が参加する
21のプロジェクトチームを中心に、
全学で『教学改革』を推進。
創設以来10年間で128回の会議を開催。
平成27年度より全学的な教学改革を推進する組織体制を構築するため、教学改革会議及び高等教育研究所を設置するとともに、
才気溢れる若手教員と豊富な教育研究実績を持つ中堅・ベテラン教員による教学改革プロジェクトチームを編成しています。
教育改革プロジェクト一覧
- 英語・グローバル教育の充実
- 初年次教育・キャリア教育を核とする全学教育の実現
- 全学的なAI・数理・データサイエンス
教育の構築と学内DXの推進 - 学修成果の可視化
- 産・学・地の連携による教育研究の充実
- 全学的なアクティブラーニングの推進
- インターンシップ制度の充実
- 専門演習(ゼミ)、卒業研究・卒業制作の充実
- 高大接続改革の実現
- シラバスの一層の充実
- 適切な成績評価の実施
- 授業評価アンケートの活用
- ラーニングコモンズの活性化
- 教員表彰制度の充実
- パーソナル・ブランド・
マネジメントプロジェクトの推進 - 教学IRの充実
- 体系的なFDプログラムの展開
- 学修成果を発揮する
各種大会・コンペティションの充実 - 教育総合改革プロジェクトの設置と
改革推進強化 - 学生の成長実感の向上を図る
課外活動・イベント等の充実 - 教学改革成果等の学外発信強化
本学では、全ての授業でアクティブラーニング型の授業を展開。
学生自身が調べ、考え、発表し、教員と双方向の「参加型」授業を全学で実践しています。
大阪成蹊短期大学
アクティブラーニングの『10の要件』
アクティブラーニングの『10の要件』
思考し、文章にまとめ、発表する
1
学びたくなる環境を作る
板書やスライドの工夫、履修の工夫などによって、快適な学習環境を整える
2
学び合う仲間を作る
アイスブレイクで緊張をほぐし、グループ構成の工夫などによって学び合う仲間・関係性を作る
3
学びを深める活動を作る
個人ワーク、グループでのワークなど、様々な活動を並列しながら、自ら学びを深めていく活動を作る
4
適切な課題を与える
思考を刺激し、学修意欲を生み出すよう課題を工夫するとともに、回の授業に必要となる後学習・復習の課題を提示する
5
思考をアウトプットする
書く、話す、聴く、発表するなどの活動を通じて、深めた思考をアウトプットする

6
成果物を生み出す
学びのプロセスや成果を可視化するものとして、様々な成果物を作る
7
振り返りを行い、更に学びたくなる意欲を生み出す
自らの成長や変化、今後の学修における課題などに気づくことができるよう、振り返りの機会を設定する
8
適切なコミュニケーション、フィードバックを行う
1人ひとりに対する丁寧な学生理解のもと、名前を呼び、視線を向けてコミュニケーションを行うとともに、学びを広げる発言、活動への丁寧なフィードバックを心掛ける
9
適切に評価する
多様な評価方法と観点を組み合わせ、ルーブリックを共有して、適切に評価する
10
認めて、尊重する
学修面における学生の努力を必ず認めて、大きく支援する

さまざまな学修成果を発揮する機会
- 大阪成蹊カップ プレゼンテーション大会
- English Presentation & Recitation Contest
- めざせMaestro! 大阪成蹊学園
ピアノコンペティション - 人間力を育む
読書コンクール - ビブリオバトル
- 卒業論文発表会
- 卒業制作展

企業や自治体などが実際に抱えている課題に対して、チームで協働しながら検証・調査し、解決のための企画の提案を行うPBL(課題解決型)授業を積極的に展開しています。
企業
栄養学科 × 日清医療食品(株)
病院食献立と治療食への展開と実践
日清医療食品(株)との連携のもと、「食事療法」に重点を置いて、常食からエネルギーコントロール食への展開を調理し、治療食について授業を展開。実際に作成した治療食を評価いただき、調理を通じて理解を深めました。

企業
調理・製菓学科 製菓コース × ビタミン乳業(株)
SR-1 成蹊ロールケーキコンテスト
ビタミン乳業(株)と連携し、オリジナルのロールケーキを制作。デザイン、材料発注、原価計算、レシピの作成、仕込みから仕上げまでの工程を、計画的で正確な作業を行い、コンテストを実施。学内外の審査員からフィードバックをいただき、優勝作品は吹田市旭通商店街で販売いただきました。

人文科学、社会科学、自然科学に関する教養から、人や社会を見つめ、感性と知的好奇心を育む科目を開講
大阪成蹊短期大学
| 語学 | コミュニケーションツールとしての語学力を修得 |
Active English
韓国語 中国語 海外語学演習 など |
| 情報・キャリア | 建学の精神を理解して、生涯学び続けるための基礎力を修得 |
キャリアベーシック
キャリアデザイン コンピュータリテラシー など |
| 国際社会と日本 | 日々の暮らしと社会との関わりを学ぶ |
暮らしと金融
ホスピタリティー論 手話コミュニケーション論 など |
| 科学と環境 | 人が健康に生きるために生命科学や自然環境について学ぶ | 日常の科学 日本の食文化 暮らしと環境 など |
| 健康とスポーツ | 健康に生涯を送るための知識と手法を学ぶ | スポーツ健康科学 スポーツ健康実技 など |
| 人間と智 | 日本の歴史の中で作り上げられた思想、文化、芸術について学ぶ | 文学と歴史 人間と宗教 心理学概論 など |
データでみる大阪成蹊短期大学の教育成果
卒業生の本学の学びに対する評価
卒業時に実施する「卒業生アンケート」では短期大学生の教育に対する高い満足度が確認され、多くの学生が成長を実感!
教育
満足度
満足度
教職員の
サポート満足度
サポート満足度
成長
実感度
実感度
入学
満足度
満足度

授業評価アンケートによる学生の授業満足度
前期・後期授業の終了時、学生が各授業を評価する「授業評価アンケート」では、短期大学生の授業や教員への高い満足度が明らかに!
総合評価
全体として、
この授業を受けて
満足した
この授業を受けて
満足した
大阪成蹊短期大学
4.38点
(+0.42)
/5.00点中(2016年比)
| 教員の授業に対する熱意を感じた | 4.41点 (+0.38) |
|---|---|
| 教員は各回の授業テーマや目標、科目 全体の中での位置づけを明確に説明し、 計画的に授業を進めていた |
4.36点 (+0.40) |
| 教員は授業の準備を十分に行っていた | 4.45点 (+0.38) |
| (授業を受け)この分野の専門的知識や 技術が身についた |
4.38点 (+0.43) |
| (授業内容が)これから生きていくうえで 役立つと思う |
4.41点 (+0.44) |
| 遠隔授業では教員は授業ツールを 適切に活用していた |
4.30点 ( - ) |
※2024年度前期授業評価アンケート(短大:全517科目)を対象に実施・回収。
※各問を各5点満点で採点し、設問ごとに全回答者の平均点より、特に評価の高かった項目を表示(抜粋)。アンケートの設計変更に伴い、一部の項目は2016年前期比を( )内に表記。
![大阪成蹊短期大学 [OSAKA SEIKEI UNIVERSITY]](/common/img/header_img_logo.png)